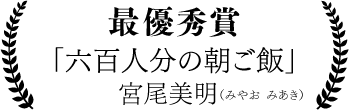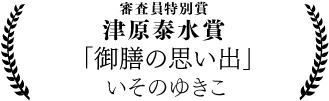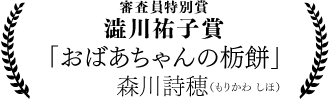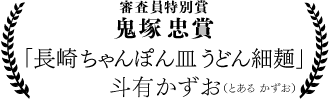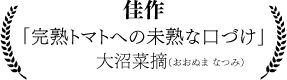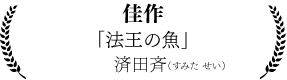幼い頃、母に連れられて朝拝(里帰り)に行った盆と正月に、御膳をいただいたのが忘れられません。母の里では、祖母が亡くなるまで、昔ながらの御膳でした。昭和三十年代のことです。三度の食事に、御膳棚から一膳一膳取り出して、囲炉裏のある口の間に運び、真ん中に蓆を敷いて鍋やお櫃や香の物の鉢を置き、祖父と叔父の御膳を頭に、家族全員が揃って向かい合いました。そこには、お腹も心も満たされる素朴で温かい食事風景がありました。
農家である母の里に着くと、私はまず従兄弟たちと、家中庭中を夢中で駆け巡りました。それから、ふと自分の御膳がちゃんとあるかどうか気になりました。それは日が落ちる頃、家の中が急に暗くなって、帯戸の漆の朱が全部闇に吸い込まれて、その取手と奥の間のお厨子の金が急にキラキラ輝き出す時です。すると私はかくれんぼを途中で抜け出し、祖母の姿を追って台所に行くのでした。くの字に曲がった体を黒っぽい衣服で包み、白髪を姉さん被りで隠し、夕餉支度に忙しい祖母は、炊き上がったご飯を、大きなお釜からお櫃へ、大杓子で移していました。ご飯の香ばしい香りが辺りに漂い、窓から斜めに差し込む夕日の中に、もうもうと立ち上がる湯気と祖母の頭の手ぬぐいの白さが、まだ明かりをつけない台所で、くっきり見えました。祖母は一心不乱でした。ご飯をお櫃に移し終えた祖母は、一度立ち上がり腰を伸ばしてから、普通の小杓子に持ち替え、またしゃがみました。仏様の飯器に盛相を使って御飯を盛るのです。
「お婆ちゃん」
その声で、ようやく私の存在に気付いた祖母でした。
「おぼくさん(御仏供さん)、上げるがあ」
「ほうや。これ、よそたら、あんたさん、ナンナ(仏壇)さんに上げて来てくれまさるき(下さいますかしら)」
「うーん、私、おばあちゃんと一緒に行く。ナンナさんとこ、暗いもん」
私は、暗い奥にキンキラキンに輝く仏壇に近づくのが、怖いのでした。
「おぼくさんを上げて来たら、御膳を出すまいか(出しましょう)」
「うん、私一緒に行く。おぼくさん、私が持って行ってあげる」
私はにっこり、祖母の手から、湯気立つ金の飯器を恭しく受け取ったのでした。
祖母は毎日、一日のほとんどを台所に這いつくばっていました。夏など、井戸のある外流しと内の竈の前を行ったり来たり。台所の土間より一段下がったところに、大中小三つ並ぶ竈に、のべつまくなし藁を焼べ、どっこいしょっと段を上がって、茹で上がった素麺の鍋を持ち上げ、湯気がもんもん上がる鍋を、ピタピタピターッと藁草履を鳴らしながら外流しに運び、ザーッと笊に素麺をあけ、苔むした木製ポンプをギィーコギィーコと漕いで素麺を冷やし、また中に入って藁を一束取り出して解きました。その合間に、藁草履を脱いで、上がり框にこれまたどっこいしょっと上って、口の間を通り、紺暖簾を潜って、暗い廊下から味噌蔵に消えました。すぐに取り出した味噌の小瓶か漬け物の鉢を抱えて現れて、また台所に下りました。その範囲を、海老腰でチョコマカ動き回っているのでした。その度に藁草履を履いたり脱いだり、脱ぐ度にきちっと草履の向きを変え、整え置いて。
御膳棚の最上段にしまってある子供用の高御膳を取り出すには、祖母が脚立にのって、つま先立ちするやら背伸びするやらしなければならないのでした。そうしてようやく、
「これがあんたさんの御膳」
と見せてくれるまで落ち着かない私でした。
夕食は、ゆったり胡坐をかいた祖父と伯父が晩酌しながら、里帰りした母や叔母と田んぼの出来や在所の近況を話していました。子どもたちもその日あった出来事を話しました。近くの川にプカプカ浮いていた魚を従兄弟のAが獲ろうとしたのを、祖父に止められた日の夕食でした。
「このいろづけ(焼き魚にたれを付けたもの)より、ずっとでっかい(大きい)鮒が、たんと(沢山)おったがに」
と、Aは御膳の上の頭も尾も皿から大きくはみ出した鰺のいろづけを指差しました。
「ほらほら、口ん中に物持って言うもんでない。食べてからにしまっし(なさい)」
と伯母が嗜め、
「まだ、ごたむいとる(文句を言っている)。あんな死にかけの魚を獲って、どうするつもりや、お前は。だらや(馬鹿だ)」
と兄のTが笑えば、
「ほうかて」といかにも残念そうなAでした。
「ほんにしても、やくちゃもないこと(とんでもないこと)になったもんや」
祖父が呟き、それを伯父が受けました。
「どっかの工場で、何か薬品を使うた排水を、川に流したんやろ、この頃度々ある」
「ほれでなんで川に魚がいっぱいになるが」
と口を尖らせたAに、Tが教えました。
「あっちやら、こっちやらに、隠れとった魚が、毒の水を飲んで苦しんで、浮いたんや」
「もう魚獲りは出来んな。それから、川で浴びるがも、明日から出来ん」
と言う祖父の言葉に、
「何でや」とAがまたもや口を尖らせました。
「魚が死んでしもうほど、汚い川で僕らが泳いだら、どんなことになるか、考えてみい。僕らも、魚みたいに、死んでしまわんなん」
と言ったTに、
「河童もか。なら、どこで泳いだらいいが」
と聞いたAの語尾は、すすり声でした。
「ほんとやね。私ら、みんな、川で泳ぎを覚えたんに、あんたらの時代に、それが出来んとは、かわいそうに」
同情を寄せたのは、母でした。その途端、
「えっ叔母さん、泳いだん(泳いだの)」
Tが突拍子もない声とともに膝立ちし、信じられないというふうに目を丸くしました。
「アラー、Tちゃん、ほんなにびっくりせんかて、川で私も泳いだわね」
「えっ、S叔母さんも」
「ほうや。昔からこの辺で生まれ育った子は、みんなや」
「ウッヘェー、おっかしい」
Tが笑うと、子どもはみんな笑い転げました。
「アラー、この子ら、何がおかしいがやろ」
母と叔母はあくまでも真顔でした。
「まだ、あんたらの海水着がしもうてあるはずや。信じられんがなら、お婆ちゃんが後で、この人らの海水着を出して見せてあげる」
と、祖母が言った時、胡瓜の糠漬けをコリコリッと音立てて齧りながら、にやにや聞いていた伯父が急に、
「アッハハ、ほんなもんまで、ようっといとるな(よく仕舞っているな)。またじしいの(よく物を始末する)お婆じゃわい。そんなことしとるさけ、土蔵がいっぱいや」
と笑い、ビールをゴクゴクッ、その飲み終えるのを待って、S叔母が聞きました。
「ここに新しい家が建ったんでないけ」
「ほうながやてこと(そうなんだよ)。お宮さんの横の田んぼに家が二軒建った。橋の脇の田んぼも売れて、あそこに建て売りが十戸も建つそうや」
「横の脇は、苗代田でないかいね」
「ほうや、よう覚えとったなあ。お宮さんの前から橋の袂まで、苗代田と決まっとる」
「ほんなら、来年からどこで苗代をしまさるがやろ(なさるのでしょう)」
「知らん。それより、苗代の横に建物があったら、苗がいいがに育つかどうか、心配や」
「ふうん、一つ何かが変わるということは、ほんなことになるがかね」
「今日の魚は、何を川に流したんか知らんが、農薬も、だんだん強うなって、蝗もバッタも少のうなって、燕が来んようになった」
「そう言や、ほうやね。近頃見かけんねえ」
「そのうち、蛍もおらんようになるやろ。もう一家に一台耕運機が入ったし、村中総出でするがは農薬散布だけになってしもうた。近頃は田んぼを真面目にするより、売ることばっかり、この辺の者は考えとる。それが一番儲かる方法でも、ご先祖様が汗水流し身を粉にして耕した田んぼを、自分の代で売って、楽をしようなどとは罰当たりにも程がある」
というような具合で食事は進むのでした。
洋食めいた物は何もなく、御飯に汁、魚に煮物に漬け物といった日本の純田舎料理、米も野菜も味噌もみな自家製でした。買う物は毎朝売りに来る豆腐と魚くらい、当時でも旧式の食生活でしたが、祖父と伯父の御膳の上に盃かビールのコップがある以外は、皿数はみな同じ、真ん中にあるお櫃やお味噌汁の鍋、漬け物の鉢から好きなだけ取って食べました。祖父と伯父以外は正座でしたが、みなが分け隔てなく自由にのびのびと話し聞く、安心した雰囲気がそこにはありました。
いつの間にか、幼い時に経験したこの御膳の食事が、私の心の中で、理想の食卓になっていました。家族みんなが揃って同じものを食べ、平等に心置きなく話し聞く食卓です。そして、家族の食べる物を自分の手で作りたい、そう夢見るようになったのは十代、もう祖父母はなくなり、母に連れられて訪れることもなくなってからでした。けれども、その理想を現実化するのがなかなか難しいことを、成人し家庭を持って気づきました。台所に這いつくばっている祖母、田んぼから帰り御膳の前にゆったり胡坐をかいた祖父や伯父、その前で安心してはしゃぐ従兄弟たち、みな平凡で幸福そのものでした。私は果たして、そんな平凡な幸せを家族に提供しているだおうかと、ふと振り返るこの頃です。
「食の思ひ出 コンテスト」
津原泰水賞
御膳の思い出
いそのゆきこ(66歳・女性)